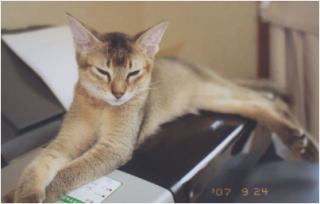|
2��
2��10���̑��̓�
  
2��9���̖锼����~�葱������́A10���̒��ɂ͂�������ς���܂����B
9���̗[���ɂ̓��O�n�E�X�ɏo�����A���̂܂܋߂��̉���ɐጩ�ɂł����A�����Ă��̖�̓��O�n�E�X�ɔ��܂��āA�R�̖X�ɐႪ�~��ςނ��܂߂܂����B
�I�V���C�ɂ́A�Ⴊ�~�肵����A�����̎R�X�͔����܂��Č������A���E�[���B
�ڂ̑O�ɂ����Ԕ������ނ������C�̂Ȃ��ŁA���L���Γ͂��}�ɐς���s����߂Ȃ���A����ɂ���̂́A�z���g�ɂ��`���C�����ł���܂��B
��̓��́E�E�E
�g�F�ɂ��ׂ�܂�����ʂɗv��܂��B
�ق�i�ؗ��ɗ����Ă���͂ꂽ���}�j�����ł́A�p�`�p�`���Ɛ����悭�͂��A���ɂځ`�`���ƓˑR�ΐ��𑝂��A�����ăS�[�S�[�A���������ƔR�������āA�����ɃV�����Ə����Ă��܂��܂��̂ŁB
����܂蒷�������܂���B
�ق�́A�����ɏ����邵�A�M�ʂ����Ȃ����ߒg���Ƃ�ɂ́A������ƕ�����Ȃ��B
�傫�ȔM�ʂ���������������������ɂ́A���Ȃ�傫�ȑ����ۑ�������B
�S���`���Ƃ����u���b�N��̑��`���}�L�����S�ɂ�����܂ŁA�g�F�̑O�ŁA�����̊Ǘ����v��܂��B

���̂������X�ɉ��p�������āA��₳�ʂ悤�ɁA����肵�Ȃ���Ȃ��B
�g�F�̑O�ŁB
���`�`���ƁA���₦�Ȃ��悤�ɁA����ڂ��A����ڂ��B
���̎��Ԃ����������I
�Ɗ�����l�́A��̓��̖����݂��Ă���B
����́A�ȒP�ɒ��ł��āA�ق��Ă����邵�A�����̂�����Ȃ��A���Ƃ��ΐΖ��X�g�[�u�Ȃł͖��키���Ƃ��ł��Ȃ��A�㎿�̎��Ԃł���B
�Ζ��X�g�[�u�͕֗��ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�g�F�̉Ƃ����A�킪�܂܂Ȗ\���V�����ƂȂ����Ȃ��߁A�������A�]�킹����Ă�����햡��m�炸�ɉ߂����Ă��܂��B
�����āA�ڂ̑O�ŐԁX�ƔR��������̌���m�邾���ł��A�y�������������ԂƂȂ�B
�g�F�̑O�ŁA�������Ȃ��ŁA�����l���Ȃ��ŁA�߂āA������ƍ����Ă���B
�ڂ��肵�Ă���B
���Ƃ��Ƃ��Ă���B
�ł��A������Ƃ����C�����ĉ̔Ԃ����Ă���B
�����������Ԃ��l���ɂ͑���Ǝv���B
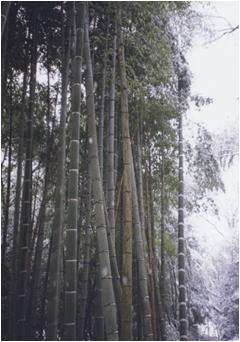
��̓��́E�E�E
�Ԃ̉^�]�ɒ��ӁB
������Ƃ̌X�ł����Ȃ�X���b�v���邩��A�C���������߂ĉ^�]�B
�ԂƂ̐M���W��V���ɖ₢�A�z���@��Ȃ�āA����������̓����œK�ł��낤�B
���i�N���}���܂̑��݂��C�ɗ��߂��ɂɉ^�]���Ă������Ƃ��A������Ɣ��ȁB
�N���}���܂��܁B
���������Ȃ��E�E�E
�o�q�`�c�n���܂̂������ŁA�X�����ׂ炸�ɏ�艺�肪�ł���B
���`�`���̂o�q�`�c�n���܂��A����͂����Ė������Ăł��i���Îԁj�����ĂĂ悩�����I
�Ɗ�����u�Ԃł���B

�S�����������I�o�q�`�c�n���܂́A�������I�I���������I
���������o�q�`�c�n���܂̐^������������u�Ԃł���B
�N���}���܂ɑ���M�����Ȃ���A��̓��͉^�]���Ȃ��ق��������Ǝv���B
��̓��́E�E�E
����Ɗ����č��܁I
�������点�ē]���I
�����ȏŁA�����������Ȃ����̂����邩��A�Ȃꂽ����ɂ��אS�̒��ӂ�����B
�s��ɂ���Ƃ��������אS�̒��ӂ��Ċ��N�����@��Ȃ��B
�قƂ�ǖ����B
������A�s��l����̂Ȃ��Ńt���t�������Ɗ�Ȃ��I
��̓������͐l�Ԃ̖{�\���������܂��@��ł͂��邪�B
��@�ɑ���{�\�Ɏ��M���Ȃ��l�́A��̓��͏o�������ɁA���`�`���ƕ����ɂ������āA�Ђ�����Ⴊ�Ƃ���ߌ��҂����ق��������V�C�B
���ƂȂ������Ă����̂������V�C�B
�����̂���������V��ł���܂��B

�u�אS�̒��ӗ́v���āA�s��Ńt�c�E�ɐ������Ă���ƁA�ǂ�ǂ�݂��Ȃ��čs������A�����Ȃ�ᓹ�Ȃ͕����Ȃ��ق��������ˁB
�����Ƀj���Q�����މ����Ă��邩���Ă������������`�����X���B
��̓��́E�E�E
���̊O�̐�߂Ȃ���A�g�F�̉Ŗ{��ǂށB
�������ѕz�����Ԃ��āA�������݂Ȃ���E�E�E
���ꂪ��̓��̖����݁B
�}�N���r�I�e�b�N�͂��߂܂���
���̂́A���m���}�N���r�I�e�b�N�ł͂Ȃ��B
�����ɂ����A�}�N���r�I�e�b�N�ł��A���R�H�ł��A�x�W�^���A���ł��Ȃ��Ǝv���B
�������A�}�N���r�I�e�b�N�̖{�Ȃ�ǂ߂A���̎蔲�������ł���A����ɂ����Ԃ�Ȃ�Ƃ��߂��H�����ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B

���́A������W�������ŁA����������Ɏ蔲�������鐫���ł��邩��A���i�Ƀ}�N���r�I�e�b�N�ɓO���邱�ƂȂ��A�͂Ȃ��獢��Șb�ł���B
����Ȏ����A�Ȃ��H�}�N���r�I�e�b�N�i�Ȍ�r�I�Ɨ����j�ɂ͂܂��Ă��܂����̂��H
�Ƃ����ƁE�E�E
�������Ⓚ���傤���ŏd�Ԏ҂��o���I�Ƃ������Ƃ������I�ɂ͈�̂��������ł͂���B
�V���̋L�ڂ���[���ǂ߂A�Ⓚ���傤���A���������Ⓚ���[���L���x�c�ŏd�Ԃɂ��������l���āA�������ł́A���S���Ă��Ă����������Ȃ��C������B
���̐l�A�悭�����҂ł�����Ȃ��E�E�E�Ƃ����̂��A�L����ǂƂ��̈�҂Ƃ��Ă̊��z�ł������B
���Ȃ��ɂ���Ń��J�b�^�l���āA���ۂɂ͂����Ƃ�������Ǝv���B
���Ԃ�A����鐔���̐��S�{�͂��邾�낤�B
�������Ⓚ�H�i�Ńq�g��l�����ʂقǂ̔_��i�Ŗ�Ɖ��߂ł���j�����o�����E�E�E
�Ƃ������Ƃ́A�v���ʂɋy�Ȃ����x�̔Z�x�Ȃ��Ɍ��o����Ă��Ă��A���R�Ȃ�ł͂Ȃ����낤���H
�����Ă��̔_�앨�ɂ͔_��������E�E�E�y����_��܂݂�E�E�E��ɂ��ǂ�����E�E
�h���܂Ƃ��F�f�Ƃ��E�E�E�ƒN����������B
�܂�_�Ŗ�̕��ʂ��A�����Ƃ��ߌ��Ƀh�o�[���Ɠ����Ă��邩��A��������Ȃ́A����u�ԗⓀ�ŗA������A�q�ɂɒ����Ԓu����Ă��A�т��Ƃ����Ȃ����i���肦��I�s���s���Ȃ킯���B��Ђ��̏����ɂ���āB
����ɁA���X�g�����Ȃŏo�Ă��郁�j���[�i�����Ă��Ɩ��X�[�p�[�Ȃ̃u���b�N�Ⓚ�ޗ��j�ɂ��A�_�h�o�h�o�E�E�E������z���ɓ�Ȃ��B
�_��Ȃ����āA�������i�́A��Ɍ��Ȃ��I�̂ł͂Ȃ����H

���́A���ǂ����������Ă���̈�N�w�X�[�p�[�ł̌���i�H�ޑ�ʒ��B���I�x���߂ł����Ɩ�����A���͒������ɂ���A���x�����ʂ��u�����A�����ꏊ�A�����v�Ȃ��������߂�]�T���ł��Ă���B
����i����}�Ŕ������ނقǖZ�����Ȃ��Ȃ����̂��B
������A�X�[�p�[�̒n���H���i����̒I�̑O�ŁA�����̂�Ƃ�������āA���x���ׂĂ���킯���B
��w��5�N�ŏK���u���K�������̕\�L�F�l�H�Ö����A�ۑ����A���F���v�̓Y�����̎�ނɊւ���u�`���e�����܂ł��o���Ă���قǂ��B
�����Ō��\������A�̂�����l�����o����قǁA��������̔��K���������A�H�i�Y�����ɑ��݂���B
�����ς��Y�ꂽ�u�`������̂ɁA���������Ƃ�����ۂǂ��o���Ă���̂́A��w�����炩�H
�ӂނӂށE�E�E�l�H���F���A�l�H�Ö����A�l�H�������A�ۑ�������E�E�ӂ݂ӂ݁E�E�Ƃ��B
��҂̒��Ⴊ�A�`���b�g�͔�������Ă���u�Ԃł���B

�q��ĂŁA�n�[�h�X�P�W���[���i�Ȃɂ��뗿�����Ȃ���m�̂��}���`���C�Ƃ����ς���I�I�j�Ȃ��O�l�����Ȃ��Ă������X�ɂ́A�����x���Ȃǂރq�}�͑S���Ȃ��B
���ɂ߂��݂�������n�j�B
���C�̂����������V�Ȃ�n�j�B
�ޗ����������ł��A�Ȃɐ��ł��[���[���n�j�B
�������̂�����E�E�E
�䂪�Ƃł́A���ŋ߂܂ł���ȏ������̂��E�E�E
�܂�A����́A�����������Ȃ����Ă������_���Ⴀ�Ȃ��C������B
�����ł́A�_��h�o�h�o�b�I�I�ł܂���Ƃ����Ă��邵�A���Ɏ����u�������ς��ɂȂ�Ή����ł���n�j�v���Ă�������ɂ́A�������H�ނ��ǂ�ǂ�w�����Ă����̂�����B
�����̐l��
�u������{�l�������ł���̂��H�������ς��ɂȂꂸ�Ɏ��ʐl���炢�鎞��ɁH���{�l�͂킯���킩���I�H�Ǝ��������[���ɋ߂������ɁI��������A�����Ȃ���Ⴂ���̂ɁH�I�����̐ӔC�ōw�����Ă����Ȃ��珟��Ȃ���v
���čl���邩������Ȃ��B
�����Ⴆ�A�����Ɛ����Ɋւ��闝�_������ē��R�Ȃ̂��B
�T���ȍ��ƂɂƂ��Đ����Ɛ����͓��`��ł͂Ȃ��B
�������n�x�̍����傫�����Ƃł́A�����C�R�[�������Ȃ̂��B
�������������̂́A�؈Ⴂ�ȋC������B
����͓��{�̖��ł���A���{�l�̊Â��̍\���ɜ���B
�H����@�Ƃ��Ę_����Ȃ�A���{�l�͓��{�̗���m�ɔF�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�H��A�����Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ����{���̌���Ȃ̂��B
��������̗A���ɗ����Ă������{�̐ӔC�ł����Ē����̐Ӗ��ł͂Ȃ��B
�����v���B
�b�����Ƃɖ߂��āE�E�E
�����}�N���r�I�e�b�N���͂��߂����R���u�����_��܂݂ꎖ���v�����ł͂Ȃ��B
�}�N���r�I�e�b�N�ɂ�����֔�������P���ꂽ���Ƃ��傫���B
���͉ߋ��R�T�N���A���܂����������Ƃ��ł��Ȃ��قǏd�ǂ֔̕�ǂł������B
���w���ォ�����������������܂��̂݁A���C�㎞��ɂ́A�ߍ��ȘJ���i�����Ζ����قږ����j�ɂ���ĉ��܂̗ʂ͑��ʂ̈�r�����ǂ�A�t�c�E�̗e�ʂł́A���������ɖ����Ȃ����A��p�ʂ�10�{�͈���ł����Ǝv���B30�{�̂�ł��������������Ƃ�����B

���v���A�����Ƃ��ُB
���������̂ӂ�ӂ�̃A�^�}�ʼn��u�n�̊O���ɏo���ɏo�����A�a�@�ɋA��₢�Ȃ�n�o�B
�����āA���̔ӂ������B�Ƃ����̂����C��̓���ł���������A���܂͂��Ȃ炸�o�b�O�ɓ���Ď��������Ă����B
�ւ�Ȏ����ɔr�ւ��Ȃ����߂ɂ́i�n�o���Ƃ���f���Ƃ��j�O�����āA���܂��ʂɈ���ŗp�𑫂��Ă����K�v������������B
����Ƃ��a���ɓ����o�b�O��u���Y�ꂽ���́A�e�ȊŌ�w����Ɂu��ʂ̉��܂������Ă���o�b�O�����炽�Ԃ�搶�̂ł��傤�H�v�ƁA�͂��Ă�������肵���B
���قǁu���C��̉ߘJ���v����莋����Ȃ���������ł��邪�A���̎���ɕ֔�ǂ͋Ɍ��܂ŃG�X�J���[�g�����̂��B
���ꂪ�I
���̏d�ǂ֔̕�ǂ��I
�������̂��B
35�N�����������Ƃ̂Ȃ��A����ȕ֔�ǂ��������I
���Ă�H�ׂ邱�ƂŁB
���ĂɎG���i��������Ƃ��A�͂Ɣ��Ƃ��A���ށj�������Đ����Ă��n�j�B
�֔�ǂ����S�Ɏ������I
���ꂪ�}�N���r�I�e�b�N�ɂ͂܂�ő�̗��R�ł���B
�������玄�̃r�I���H�̓��X���n�܂����B
�}�N���r�I�e�b�N�̎��H���V�s�ł��邪�A
�������߂��u�ݖ{�t�q�̕�炵�Ƃ��͂�v�����Ёi1600�~�j
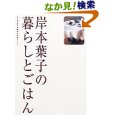
���ꂪ��ԁB
�_���g�c��ʁI
�������A�ݖ{�t�q����́A�����ɂ������N���r�I�e�b�N�ł͂Ȃ��B
�ݖ{�t�q����́A40�ő咰�����i�����ɂł��������咰�Z���j�̂n�o���A����ȗ�������̎w���̂��ƁA�Ɩ������߂�H���Ö@�����H���Ă���B
�ݖ{�t�q����̒��q���G��ȗ��R�́A������w�ł��t�c�E�Ɏ��s�ł������ȓ_�ł���B
�Ƃ������A�t�c�E�ɓ����������t�c�E�ɗ����ł��ăt�c�E�̐H�ނȂ��A�������Ă���ł���`�B
�ƁA���肰�Ȃ��A�������A�|�C���g���͂����Ȃ��ʼn�����Ă���_�ł���B
�ݖ{�t�q����̐H�Ɋւ��钘��́A���ɂ��������āA�ǂ������������߂ł��邪�A�Ȃ��H���������������@���悢�̂��H�Ȃ��H���������������@�ōs���̂��H�����ƕ��͂̂ǂ����ɏq�ׂ��Ă���̂����A���������ɓ��������Ȃ��B
�c�{�͐����ɂ���߂���A�\�ɂ͏o���Ȃ��B
����`�`���Əq�ׂ�B
��₱�����菇����؏����Ȃ��B
���Ԃ��ď����Ȃ��̂��낤�B
�ǎ҂Ɂu����Ȃ�����ȁB���N�I�^�N����Ȃ����B�����܂ł������邩��I�킽���ᓭ���Ă���I�Z�����I�v�ȂǂƐ�Ɏv�킹�Ȃ��B
�N�ɂł��ł������Ɂi�z���g�̓`���b�g�C������K�v�͂���̂����E�E�j������Ă���B
���̓��]�����ȕ��͗͂��A�ޏ�������o�̍ˏ��ł��鏊�ȁB
�Ȃ̂ɁA�ݖ{�t�q����́A����o�I�ˏ��I�����炬�炳���Ȃ��B
�ݖ{���m�M�ƓI�Ȓm�\�ƂȂ̂́A�ǎ҂��u�}�N���r�I�e�b�N�v�ƕ��������ł߂������ȁA�Ƃ��������育�݂������ȓ_���A�������g���߂�ǂ������̂�`�Ƃ��A�����ł��Ȃ��̂�ˁ`�`���ƁA������U���悤�ɉ�����邱�ƂŁA���̂悤�Ȏ蔲����w���t�@���ɂ��Ă��܂����Ƃ��낤�B
�e�L�X�g�́u�ݖ{�t�q�̕�炵�Ƃ��͂�v���̈���ŏ\�����Ǝv���B
�b���̓`���b�g����邪�A
�ݖ{����̒����u����n�܂�v�u40�ł���ɂȂ��āv�́A��t�ɂƂ��āA�����҂��ǂ̂悤�Ȑ��_�̎����ɂ��炳��A�ǂ̂悤�ɂ��Đ�����Ӗ������߂邩�H�̋��ȏ��ł���B
���ɂ��Ă̔ޏ��̋L�ڂ͂������I�������I�ɐs����B�����ė��h�ł���B
�܂˂̂ł��Ȃ����Ƃ��B
����ς�˕Q�ȂB���̂ЂƂ́E�E�E
�}�N���r�I�e�b�N�ɂ��āA���̂ق��̒���ł́A
�r�I�Ɋւ����N�����b�T���̓��W���A�����G�v����́u�e�H�̂����߁v�V���[�Y����낵�����ƁE�E�E�E
�������A������w���蔲���Ǝ������Ȃ����}�N���r�I�e�b�N�����H����ɂ́A
��͂��ݖ{�t�q������{�B
���ЂƂA�u�}�N���r�I�e�b�N�͂��߂܂����v�A�X�y�N�g�i�I�[�K�j�b�N�x�[�X�ҁj���悢�Ǝv���B������A���s���₷��������Ă���B���̖{����ł��\�����Ȃ��B
�������E�E�E
�����Ɓw���������ڂ�ȃL�����A�E�[�}�������x�}�N���r�I�e�b�N���H���@�I
�����w�삷���}�N���r�I�e�b�N���ǂ��̎蔲�������@�I
�܂��ł��ȁE�E
�@��{�͌��Ă𐆂��B
������}�N���r�I�e�b�N���ۂ��Ȃ�܂��B
���Ă����Ăɕς��邾���B����́A�N�ł��ł���Ǝv���܂��B
��������n�߂܂��B
�������ɂł����s�ł��܂��B
���ꂾ���ňꋓ��90���������ŁA�}�N���r�I�e�b�N���ۂ��Ȃ�܂��B
�o���G�[�V�����ɁA��������A�͂Ɣ��A�Ђ悱���A���������邱�Ƃ�����܂��B
���ĂƂ��ԕĂƂ��������Ă��܂����B
�Ȃ炩��
���̕��ʂ��́A���ю��Ԃ��́A�Ă����Ă������́A�Ή������̃C���C���������Ă��܂����A�������������B�܂����������I�����l���܂���I����ȓ�����Ƃ͖����I
�������Β����ł��܂��B
�Ƃ������A��x�����s���Ȃ��Ō��Ă��ӂ����理���R�c�Ȃǂ͂���܂���I
���x�ł����s���āA���x�ł����肩�������ƂŁA��ł��܂��B
���A���肸�ɉ��x�ł����s����̂ł���܂��B�����������V�C�B
�i���͖�����������ł��B�����b���������s�ł��j
�Ȃ�ǂł������܂����A���Ă𐆂��̂̓R�c��������������܂���B
�N�ɂł��ȒP�ɐ����܂��B�S�Ȃׂł��y��ł����ъ�ł��B
�������������́A�����Ŏ��s�������˂Ȃ��������烈���V�C�B
���s�������āA�ǂ��Ă��ƂȂ��B�H�ׂ邱�Ƃ͂ł���B�H�i�ɂ͈Ⴂ�Ȃ���ŁB
������������A�����𖡑X�`�̒��ɂق肱��ŎG���ɂ���B
�ׂ��Ƃ�˂��Ƃ萅���ۂ��Ȃ�����J���J���`���[�n���ɓ���Đ��C���Ԃ��Ƃ��B
���邢�͗①�ɂɓ���Ă����ƁA�ł��Ȃ��Ă��傤�ǂ�����ɂ��܂�B
���ɁE�E�E
�A���������ݖ��A���A�|�A���A�����A���X�Ɍ��肷��B
���w����������߂�B
���ꂾ���ł��A����ƁI�I�}�N���r�I�e�b�N���ۂ��Ȃ�܂��B
�}�N���r�I�e�b�N��20���́A�������Ō��܂�I
���ꂶ�Ⴀ�H�������ǂ����邩�H
���́A���Ⴟ����ƁA�ӂ肩����u�V�}�������̂��Ɓv�u�ق��v�u�������₤�ǂ�X�[�v�̑f�v���������̂ɂ��`�`���ƁI�����Ă������A
�R���\�������A�������̂��ƁB
����Ȃ���A�������Ǝg���Ă����̂��B
��w��30�N�͎g�������Ă����Ǝv���B
���ꂪ�A���w�������Â��łȂ��ĂȂ�ł��낤�B
���������߂�ƂȂ���u�������ǂ�����̂��H�v���؎��ɍ������������ƂȂ�B
�܂��I
���X�`�B
������C���R�A���߁A����Ԃł��������B
����́A���Ԉ�ʂ̐��������������{�ɂ����{�̊�{�B
�u�C���R�͎ϗ��܂��Ɉ����グ��v�Ƃ��A�u���z�͂��������ςȂ����Ɓv�Ƃ���ؖ����B�܂����������I�����܂��Ɉ����グ��I���ƁH����Ȃ̖����I��������I
�C���R�ł���A���߂ł���A���z�ł���A��ƈꏏ�ɂ��������Ō�܂ŎςāA���X�`�ƈꏏ�ɁA���`�`��ԐH�ׂĂ��܂��B
�C���R���J�c�I���������Ƃ���������グ�邾�ƁH�H���������Ȃ��I
�u������v��Y�ꂽ�̂��H
���{�l�̋N���ł���u�卪���V�v��Y�ꂽ�̂��H�H
�_�V���̂ĂĂ����킯�Ȃ������B���������Ȃ��I
���z�͎ύ���łł͂����Ȃ����ƁH�H
���܂݂������邾�ƁH
�t���b�I����Ȃ���W�Ȃ��B����Ԉꏏ�ɐH�ׂ�̂��I������܂��Ń����V�C�B
��ԃ_�V�A��ԃ_�V�Ȃ�ăv�����ۂ����ƌ������ǂˁA�u�V�܋g���v�ł���U�����ŋU�����Ă�����ł����I�H
���������u�D��g���v�ŁA���肪�������ċU�҂̂�����H�ׂ������Ă����H�ʂɂ͋C�̓ł����A
���F���{�l�̖��o�ȂA���̒��x�̃V�����m�ł��낤�B
�J�c�I���C���R�����z���ꏏ�Ɏύ���ł��肱��H�ׂ�B
���̂ق����J���V�E��������ς������H���Ĉꋓ�����ł͂Ȃ����B
���łɁA�ϕ��Ȃ��E�E�E
���͖��X�`�����Ƃ��ɁA�ꏏ�ɂق肱��ŎςĂ��܂��B
��������ƃ_�V�����݂��ށB
�ϕ������A����������ƔZ�����t���ɂ������Ƃ��͂��ܖ��Əݖ������傿����ƐU�肩����B�|�C���g�͂悢�ݖ����g�����Ƃɂ���B
�ݖ��Ƃ��ܖ��ɂ͂������������ق��������悭�Ȃ�Ǝv���B
����ɁE�E�E
�`���[�n���Ƃ��u�����߂��́v�S�ʂɂ��āB
���̖��t�����A���w�������Ȃ��łł��܂��I
�����Ⴑ�A���C�V�A�����݂��������A�J�b�g�킩�߁A�����C�V�B
�����������f�ނȂǁA���Ƃ��Ƃ��������݂���ł���ޗ����ꏏ�ɂ����߂�ƁA���R�ɒ������������o����Ė����Z���ɂȂ�B
�����߂�Ƃ��ɏݖ��A���ܖ��������������Ƃ��炷�B
���������ƁA���܂˂��ƁA�ɂ�A���ڂ��A�Ȃ��ꏏ�ɂ����߂�ƁA��������������Ђ�������Ă��܂ݐ��������o����邩��A���w�������Ȃ��Ă��\�����������B
���̓����S�����A���f�X�̊≖���g���Ă���B
�B���܁`�����ɂ́A���[�v���V���K�[�ƃI�[�K�j�b�N���[�Y���A�v���[���B
�����g�������ށB
���̂Ƃ��A���ȕ������i�O�g���Y�I�j�ƁA���傤�������i�₦�Ǘ\�h�I�j�ƁA�����i�R�E�l���L��j���܂��܂��B
������w���Ȃ����傤���g���̓�������I�x�Ɩ��Â��܂��B
��������������݂܂��B
����ɁI����ɂ́A
�I�[�K�j�b�N�V���A���ɓ��������������̂�H�ׂ܂��B
���̂Ƃ��A�Â݂��`�g����Ȃ��ȁE�E�Ɗ������ꍇ�́A���[�Y�����ЂƂ܂݁i�v���[���ł����[�v���ł��n�j�j�����܂��B
�s�̂̂��َq����߂�ƁA���������f�p�ȊÂ݂ɂ͔��ɕq���ɂȂ�܂��B
�l�Ԗ{���̖��o���������܂����ƁA�Ƃ��ɊÂ݂ɂ͕q���ɂȂ�悤�ȋC������B
���Ȃ��A���[�Y���A�v���[���A���[�v���E�E���ꂼ������ɊÂ݂��Ⴄ���ƂɋC�����B
���������o�����āA�l��������Ɠ������C���ɂȂ�܂��B
�܂��A�s�̂̂��َq������ɂ��������̊Â݂Ŕ����Ă��邱�Ƃɂ������܂����E�E�E
�C��Ƌ��Ɠ�
����͊ȒP�B
�ŋ߂̃X�[�p�[�ɂ͎Y�n�ƗL�@���ʂɖ��L��������L�x�ɂ���B
������ۂ̃f�p�n���ɂ�����B
���R�H�̓X�������w�O�ɂ́A��Ƃ���B
�T���A�܂��܂��A��������܂��I
�����ɂ͉��H����Y�����Ȃ��̓��Ɩ�������Ƃ�����Ă��܂��B
���Ƌ����Y�n�����i���Ȃ玔�����L�@�j�̂��̂������Ƃ���B
������A���Ɠ���͊ȒP�ł��B
���͂����B
�l�i���������ǂ����H�Ȃ�ł����A���܂荂���Ȃ��ł��ˁB�͂āH�s�v�c�E�E�E
������������A���{�Y�ʼn��H���Ȃ��A�Y�����Ȃ��ŁA�\���͐M�p�ł�����̂ł����āA�������l�i�͍����Ȃ��B
�t�c�E�́A�����ƍ����Ƒz�������ł��傤���E�E���ۂ͍����Ȃ��B�͂āH�H
���t�[�̃I�[�N�V�����ł��L�@��͔����Ă��āA���������A������萔���Ȃ��A�ł��A���\�育��ȉ��i�B�ĊO�₷�������肷��B
���t�[�ŃI�[�N�V�������Ă���X���āA�����Ɋy�V�ɂ��o���Ă����肷�邪�A���R�H�̗��������ȁ`������V�܂�����B���̈Ӗ��ŁA���ɐM�p�ł��邨�X������܂��B
���������X���炿�傭���傭���B���Ă��A�������ăX�[�p�[�����オ�肾�����肷��B
�ǂ����Ă��Ȃ��H�H�E�E�E�E�s�v�c��Ȃ��E�E�E
���Ԃ�A����͂ˁB
�R�[�v��R���r�j�ɏo������ƁA����Ȃ����̂����łɃC�b�p�C�����Ă��܂����炩���H
���́A�������ŃX�g���X�������Ă���Ƃ���������āA���َq�Ƃ��X�i�b�N�Ƃ��A���܂݂Ƃ��A�r�[���Ƃ��E�E�E�߂��炵���������ꏏ�ɔ����Ă��܂����獂�����H���ȁH
���̓_�A���R�H�̓X�ɍs���ƁA���������v��Ȃ��������܂���������Ȃ��ŁA��������ړI�����Ŕ�������A�����H���ȁH
�����́A�t�ɁA������Ȃ��Ȃ����Ǝv���B�������ɍs���Ƃ��ɁB
�����ɁA�{���́A���{�@�����}�N���r�I�e�b�N�u�����܂Ƃ߂܂��B
�������������ɁA��Ԃ��������ɁA�_�o���g�킸���}�N���r�I�e�b�N�����H����ɂ�
�@ ���Ă𐆂������ł��悢�B
�A �������i�_�V�j���A�C���R�A���z�A���߂łƂ�B���ꂾ���ł��悢�B���ɂ悢�B
�B �ϕ��́A���X�`�̃_�V�����p����B�u�ߕ��́A���Ⴑ�ƍ��C�V���ꏏ�ɂ����߂Đ��ݏo�������ł��悢�B�ݖ����㓙�ł��肳������Ζ��͌��\�C�P���B
�C ���R�H�̓X�͂ǂ��ɂł�����B�X�[�p�[�ɂ��L�@�͔|�̓��Ɩ�͂���B�����Ēl�i�͎育��ł���B������A���������X��`�������ň�i���}�N���r�I�e�b�N���ۂ��Ȃ�B
�D �}�N���r�I�e�b�N�̂��߂��u�������v�����B�Ƃ������A�}�N���r�I�e�b�N�̂��߂��u�������v�͂��Ȃ��B�Ƃ����X�^���X�������V�C�����B���̂ق�����y�₵�ˁB
�܂�A�X�i�b�N�َq����߁A�o�������̑y����߁A�����ƃ^�o�R����߂邾���ŁA�Ȃ܂��}�N���r�I�e�b�N�����炷������A��قnj��N�ɗ��ӂ��Ă���Ǝv�����ǁB
����������I�������������Ȃ��I�p�����厖�B
����́A�����蔲����w�̋ɈӂƂ��Ċ�����_�ł���܂��B
�E ���������E�E���ݕ������ǁA�Ԓ����悢�B���Ȃ������悢�B�炵���E�E�E
�ȏ�E�E�E�{���̍u�`�͏I���������܂����B
�V�l���͂Ƃ��Ă��[��
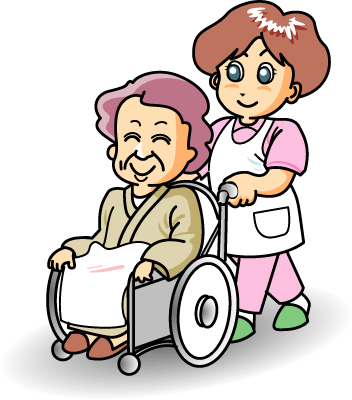
���́A�O�g�s�̉��ی��F��������Ă���̂ŁA�V�l����͂����Ƃ��[����Ȃ��E�E�Ɗ�����B
�[���Ƃ��������A�����ς܂��Đ؎��Ƃ����ׂ����H
�i�V�l���ƂЂƂ�����ɏq�ׂ�̂́A������̂��������ɑ��Ď��炩������܂��j
�V�l������A���ɐ[���Ő؎��ȗ��R�́A�\�Z�i�܂�s�̍����j�ƁA�ŋ���[�߂���J���l���ƁA���̗\�Z���g�����������V�l�l���i���m�ɂ͉�����̂͘V�l�����ł͂Ȃ��j�̊������A�N�X�A�}�s�b�`�ŋt�]���āA���̌X������������Ă��邩�炾�B
�����āA���̋t�]�̍\�}�́A���̂����i�v�ɔ��]���Ȃ��ł��낤���Ƃ��A�m�M�ł��邽�߂ł�����B�Ȃ��Ȃ�E�E�E
�J���l���́A���ꂩ����A�܂��܂���������ł��낤�B
�ŋ���[�߂������i�Ƃ����������������Ɖ҂��ł���j���Q���j�́A�ǂ�ǂ�B
�j�[�g�Ƃ��A�t���[�^�[�Ƃ��A�l�b�g�J�t�F��Ƃ��A��҂ɂ����炸�����N�̃z�[�����X���ċ}�����ł�����A�ŋ���[�߂邱�Ƃ��ł���j���Q���́A���q���Ƃ����l���������̂������O�����Ƃ���ŁA�����Ă���̂͊m���ł���B
�ŋ��́A�撣���Ă������������Ł������ł��炽�瑝�ł����Ƃ���ŁA���قǂɑ����Ȃ��B
60�Έȉ��̃j���Q�������Ȃ����邽�߂��B
����A������V�l�́A�}���ɑ������āA���̂܂܌����������ő���������B
����p�͐����悭�������A
���̍����́A����܂��}���Ɍ������A
�����āA�܂��Ȃ��j�]����B
���������\�����A�ڂ̑O�̌����Ƃ��ĔF���ł���B
���ی��F��������Ă���ƁA���T�A���T�A���������R�����������A���͂��̂��тɁA�Ȃ������̗a���c�����[���ɕK���ŋ߂Â��Ă����̂��A�ځ`�`���ƂȂ����ׂ��������߂Ă���悤�ȁA�ߎS�ȐS���ɂȂ�̂��B
�S�����X�Ƃ���B
���{�ɂ������Ȃ��Ȃ���E�E���āA���������Ȃ�Ȃ����H
�ƁA�Ȃ��A�S���ƂȂ��Ȃ��Ă��܂��B���͍����n�R���ȂB
�����āA���{�̊�@�́A�ǂ��ɂ��邩�Ƃ����ƁE�E�E
�P���v�Z��1���Ő��v�ł��錋�ʁi�����������H���ی��̍����͔j�]���A�ŋ��͌͊�����̂��H�j�ɁA�����̂قƂ�ǂ����S�Ŗ��h���ȓ_�ɂ���B
���͖{��Ƃł����������H
����Ȃ�m����I�E�E�E���Ă����A���l���Ƃ��Ă�肷�������m�ɂ���B
���V�l������Ă���ƒ�́A�����������������炨����������A
������́A���ی��i�܂�ŋ��j����x�����Ă���̂��H
�����̋��z��m���Ă���B
���R�Ȃ���w���v��H��A�I���c����I���c������p��������x�����̂��H
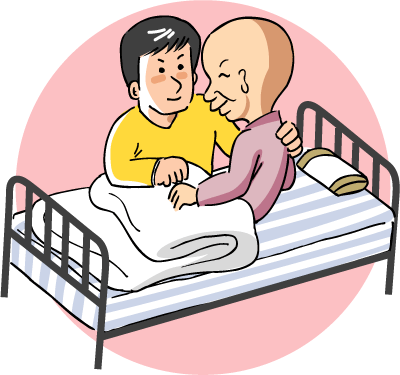
���ی��̕��S������������m���Ă���B
�ł��A�����łȂ��ƒ�́A�V�l�ЂƂ�����̂ɂ����炩���邩�H
�����炭�m��Ȃ��Ǝv���B
������͂���Ă��鎩���̖��Ƃ��āA�Ƃ炦�Ȃ��Ǝv�̂��B
���͉��ی��F���Ƃ��āA���T�F�肷��v���҂�25�l�Ƃ��āA
���`���ŏT��125�l�A�Ƃ������Ƃ͌���500�l�B
��p����l�ɂ�����30���~�x���Ƃ��āi48���ȏ�����肦�邪�j��1500���~�����E�E�E
�ƁA�����Ĉ�N���ƁA1��8000���~������B
���ɁA���T�̔F�肪30�l�Ȃ�2��1600���~�Ȃ̂����E�E�E
�܂��N�ɂ��悻2��������Ƃ��āA10�N�ł�20���~�����E�E�E
�ƁA���R��20���~�Ƃ��������߂�B20���~�E�E�E
�c�ɂ̒O�g�s�ł����Ȃ���A�s�S�ł́A�����ƍ��z���낤�ˁB
��s�s�قǐl�����x���������A�v���V�l���������A�قƂ�ǂ��j�Ƒ������B
�����āA�V�l�Ȃ�����ی������ł͂Ȃ��A��Õی��̓��`�����K�v�Ȑl�������B
�a��̈��������Ƃ��Ɉ�Õی����g���ƂȂ�A���̔{�A�������͂��̂Q�`�R�{�]���ɂ�����������B
�Ƃ������Ƃ́A�������Ƃ�40���~����60���~�����E�E�E�ƁA���̐����߂�B
����ȂɘV�l�̕}�{�ɗ\�Z���������Ȃ�A�������ꂵ���Ă�����܂��B
�����̐�����āA����N���Ȃ�āA���̂܂����E�E���Ă��Ƃł͂Ȃ��̂��Ȃ��E�E�N����������߂�ׂ����E�E
�ƁA���Ȃ�s���ɂȂ�B���́A�����S�z���Ȃ̂��B
�ł��A�N���͂��炦��ƐM���Ă���B�M���邵���Ȃ��B
�����łȂ�������A����ȂɔN�����������������Ă��鎄�Ƃ��ẮA����R������Ȃ��I
�����ŁA������ƁA�u���C�N�B
�V�l�ɂ܂��l�����́A���Ƃ��Η]���������炠��̂��H
����́A���ώ����܂ł��Ɖ��N�����邩�H���ώ����ƒP����r����̂łȂ�
����70�̐l�̕��ϗ]���͂����炩�H
����80�̐l�̕��ϗ]���͂����炩�H
�Ƃ����v�Z���ŏo���ׂ����Ǝv���B
70�A80�A90�̂��ꂼ��̗]���́A���{�̑S�l����ʂ̕��ώ�������̎��Z�����A���Ȃ�傫���ƍl������B
��������������҂̉��ƈ�Â��A�J���҂ł����X�̌��ɂ������Ă���̂��B
�����āA���ɂ�����d�ʂ́A�N�X�d���Ȃ�A
�����ۂ��ŁA�x���邱�Ƃ��ł��錨�̐��͔N�X���Ȃ��Ȃ�B
���q����Љ�̌����������ł���B
�ł��A�����Ă��̐l�́A��������������@���A�^���ɗJ���Ă��Ȃ��悤�Ɏv���B
�C�ɂƂ߂Ă���l���āA�ʂ����ĉ��l����̂������H
�����A���{�l���Ď������i�Ƃ����������̉Ƒ����j���ʂ��Ȃ��ƁA��ɁA���[��l���Ȃ��Ȃ��E�E�V�~�����[�V�����͂̓g�R�g���I�[�����Ȃ��E�E�E�Ǝv�����̂́B
�E�����v���҂����������Ƃ��́A�ޏ������̔����������Ƃ����B
�����͐E����13������B
�N���30�Ό㔼����40�Ό㔼���B
���̂������N�A�N���̕v�A�ƁA�n���邢�͎��Ƃ̗��e�̂����ꂩ���ˑR�ɓ|��Ă���B
�J�Ƃ��Ă��炢�A�q��Ē��̎�w�������̗p�����̂ŁA�E�������͉Ǝ������Ȃ��o���Ă����B
���������Ɛ�Ǝ�w���������`�������A�撣���ďo���Ă����̂��B
�����āA�ޏ��炪�d���ɂ悤�₭�Ȃꂽ�ȁ[�Ǝv������I��삪�n�܂�I
�E�������́A���ǂ����������āA���[����ꥥ���ƁA�肪������Ȃ��Ȃ����Ƃ���ɁA
����ǂ́A�ƁA�n�A�v�A�������͎��Ƃ̗��e���|���B
���N�A�N�����K���|���B���N�����������B
����́A�E���S�����A���������N����炵�������Ȃ��B
�Ȃɂ���40�㔼������ˁB
�Ƃ������Ƃ͐g���ƂȂ�V�l��70�Ό㔼����80�Ό㔼���B
���肦��b�Ȃ̂��B
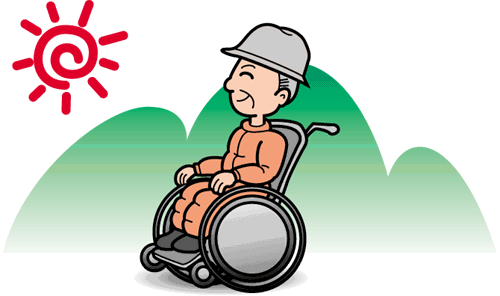
�����āA�����̂����I
�E�������́A�Ƒ��ɂ����������v���҂�������A�ˑR�A�ق�ƂɓˑR�I�o��I���Ă������Ԃ��܂������\�������A������ۂ������z�������A�����Ă��鎞���������ɂӂ��Ă킢���v���̌������A�قƂ�ǎ�����Ȃ����Ƃ��B
�ޏ���͌����ɁA�B�X���X�Ƃ��ĉ���������A�݂̂��܂�A���̂܂ܖ|�M�����B
������ˑR�I
�V�l�͓|���I
�O��܂Ō��C�ɁA���T�̔��d���̒i��������Ă����V�l���A���̒��ɂ͓|���̂��I
�����āA���̂܂܁A�Q������ƂȂ�B
����́A�����������낤�Ǝv���B
�l�ԂȂ���N�ł��͂Ƃ�̂��B
�V�l�̐ӔC�ł͌����ĂȂ��B
�V�l�������b�ł͐�ɂȂ��B
�V�l���|���̂́A�ȂɂтƂ��\�����\�z���ł��Ȃ��b�ɈႢ�Ȃ��B
������܂����B
�ˑR�̂ł����Ƃł���B����́A�ǂ̐E���ɂƂ��Ă��E�E�E
�������A�S�̒��ŁA�\�����\�z�����Ă��Ȃ������E�������̐S�́A���̓�����o�����X�������A�|�������܂܉E����������E�E�E�����āA��x�ƋA���Ă��Ȃ������ȓ��X�̖��c��ɂ���ŔߒQ�ɂ����B
���ꂪ�A���{�̌����Ȃ�ł��傤�B
���ꂪ���{�l�Ȃ̂��B�Ǝv���B
�Ȃ�ŁH������Ƃł��A�������������Ԃ�\�z����Ȃ�A�S�̏������ł��Ȃ��낤�H
�`�b�g�n�A�������������������邱�Ƃ��A�o�債�Ă��Ă��悩�����̂ł͂Ȃ��̂��H
���{�l�Ƃ́A�R�������鎩���ڂ̑O�ɁA�̕������̖т��������A�߂�߂�Əオ��Ȃ���A�ؑ��Ɖ��͔R�Ă���I���Ă������Ԃ�z���ł��Ȃ�������������Ȃ��B
�V�l�����܂ł����C�Ȃ܂ܒ������ł���H�����������肦�Ȃ��b�B
��ɂ��肦�Ȃ��b���B
����𢂻��Ȃ̂��肦�Ȃ��I����Ă����ς�Ɣے�ł���l�B
�u���₢��A���C�Ȃ͍̂������ŁA���Q������ɂȂ邩�������B���ꂪ�����ł����������Ȃ��v
�u���s���ɂ������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��v
�u������삪�K�v�ɂȂ��āA�Q������ɂȂ��āA�{�P����ǂ�����H�N���߂�ǂ�����H�v
�u�n�ƌƂ������ɉ�삪�v��Ƃ��́A�ǂ������炢���H�v
�ƁA���߂ĐS�̂Ȃ������ł��A�����ł����E���͈�l�����Ȃ��B
���Ȃ������Ȃ��E�E�E�����̈�l���E�E�E
���ꂪ���{�̓��{�l�̌����ȂƎv���B
�E�������́A������A�ˑR�A�����������A���]���A�|�M����A�����ɂ݂̂��܂��E�E�E�����܂������ɂ��������ĉj������E���͑����Ȃ��B�����Ă��͐���ɒ��ށB
�ł��A
���ꂪ��w���q��Ă��Ȃ��瓭�����Ă�������������ȂƎv���B
������\�����ĐS�\���ł���]�T�Ȃ�āA�q��Ē��̎�w�ɂ͑��݂��Ȃ�����B
�����āA�����Ƃ����Ɠ˂��l�߂�A���������̘V��͂ǂ�����̂��H
�V�~�����[�V�����v��i�������܂߂ĘV�l�{�݂܂Łj�ł��Ă���E���́A�����Ə��Ȃ��B
�����Ȃ�ł���E�E�E
���������킯�Ȃ�ł���E�E�E
�Ȃ��H�����ɂ�13�l���E��������̂��E�E�E
���̗��R�́E�E�E
�����̎��@�Ȉ�@�̂悤�ȗ�אf�Ï��i���Ґ����킸���ȃq�}�`�`�ȓc�Ɉ�ҁj�ɁA
�Ȃ�ŁH�H13�l���E�����v��́H�����ł���H���̔����ł����������B
�ʂƌ������Ď��Ɍ�����y������B
���͎��ۂ����܂����B
�u�I�^�N�E�����������܂���v�u�I�^�N�݂����ȓc�Ɉ�҂��Ĕ����ł��\���ł���v
�����ł��B
���̂Ƃ���I
�q�}�������@�ł�����E�E�E
�����̐l���łn�j��������܂���B
����5�l�ł��U�l�ł��n�j���Ǝv���B
�ł��A���͏����Ǝ������Ȃ���A�q��Ă��Ȃ���A�������I�Č����̌�������m���Ă���B
������n�̊������̓��a�����̒n�����������Ă����B
�Ђƈ�l���Ŋ����}����f�����̏L�C�Ɖ��O�̋��낵����̌����Ă���B
���a���������N�����N���������ƁA�Ƒ��̐S���ǂ��܂Ŕ敾���A�����݁A�ǂ��ɂ����邩�H��̌����Ȃ��Èł̋�ɂ��킩���Ă���B
�ǂ�ꂪ�A�ǂ�ꂾ�Ǝ��o���邱�Ƃ���ł��Ȃ������B
���X�����z����̂ɂ��������ς��B
��l�̘V�l�̖������A�����ɉƑ��̋C���������߂��邩�A���̏d�ꂵ����m���Ă���B
�����āA���̂Ƃ��������̌��ɂ�����d�͂�������̂��̂���m���Ă���B
�q��ĂƁA�Ǝ��ƁA�V�l�̉��A���������̏d�͂ɑς��āA���̂����œ������Ƃ��\�Ȃ̂́A������������ꂽ�j���Q���������Ǝv���B
�@�d���̎��͂ƁA�A�Ǝ��̒i���ƁA�B�^�t�Ȑ��_�͂ƁA�C���x�ȓ��̂����������B
���́A�ǂꂩ�������Ă��A�d���͐�ɑ����Ȃ��B
�ǂ̈�������Ă��d���𑱂��邱�ƂȂǓ���ł��Ȃ��B
�d���̎��͂ƒm�\�A���_�́A�̗́B
���́A���̂S��₦���L�[�v���u���b�V���A�b�v���A�~���˂Γ����Ȃ��B
�S�����������Ɉێ����Ȃ���A���V�l�����������܂܂œ������Ƃ��ł��Ȃ��̂��B
�E���Ǝ��̔N����l����Ɓi���ϒl��50�ɑ傫���߂Â��܂������˂��j�E�E�E
13�l�̐E���̉Ƒ����A�������ꃖ���̂������ɁA���̔����������Ɠ����ɓ|��邱�Ƃ����āA�܂������s�v�c����Ȃ��B
�����炱���A
�����́A�E����13�l�ł�14�l�ł���������Ƃ́A�����Ƃ��v��Ȃ��̂ł���B
���āA���̗��R�ł��邪�E�E�E
�b�́A���q����Љ�̊�@�I����A�����ԉ����ɂ��ꂽ���A
�����������A�V�l���ɔ����ĐE������錻��́A�߂��炵���Ȃ��Ǝv���B
���ɏ���͕K�{�ł���B
�ǂ̐E�����A�d������߂ĉ��ɐ�O���Ȃ���A�����������̂Ȃ����Ƃ��Ǝv���B
���̂Ƃ��A���́A�E���Ɏd������߂��ɁA���Ƃ��T�ɂP��ł��A���ɂQ��ł��������瓭���ɗ��Ăق����Ɗ���Ă���B�������ꎞ�Ԃł���������A�d�����ɏo�Ă��Ă��炢�����B
�ǂ�Ȃɂق��ڂ��Ƃł���������A�d���𑱂��Ă����悤�ɋF���Ă���B
���[�[���ꂶ��A13�l���E�����v�闝�R���A�~�i�T�}�ɂ킩���Ă��������Ȃ��ł���ˁH
�Ȃ�ŁH13�l���ق��Ă���̂����H�H���Ďv���܂���ˁH
���`�`��E�E�E�킩��₷�������Ƃł��˂��E�E�E�E
���Ƃ��A5�l�̐E���ɓ����Ă��������Ƃ���B
������A���̂�����1�l����삹�˂Ȃ�Ȃ����ԂɂȂ����Ƃ���B
�����͂T���̂P������20���̌��@�ƂȂ�B
20���̌��@���A�̂���̂S�l�ł܂��Ȃ����Ƃ͕s�\���B�����Ƃ��n�[�h�B
�����ɂP�l�ق����낤�B���̐E���ɂ͎��߂Ă��炤��������Ȃ��B
�������A����13�l�̐E���ɓ����Ă��������ꍇ�Ȃ�A
1�l����쎖�ԂɊׂ����Ƃ���B13���̂P���V���̌����ł���B
�c���12�l�łV���̌��@�����߂邱�Ƃ͓���Ȃ��B1�l������0.5���̕�[�ł���B
��������쒆�̐E���ɂ́A�T��1��ł��Q��ł��������͈͂Ŏd���𑱂��Ă��炤�悤�A�y�ȏ����������߂邱�Ƃ��ł���B�s���̂������ԑт��Ă��邱�Ƃ��\���B
�����ς��������āA�V���ȐE�����ق������A�����B�Ǝv���B
�Ȃ�ŁA����Ȃ���������Ȃ��Ƃ����̂��H�Ƃ����ƁE�E�E
�V�l�����ĂˁB
���`�`�`���ƁA�����24���Ԃ����肫��̐����ƁA��삷��l�Ԃ̐��_�������Ȃ��Ǝv������ȁB
�_�o������ւ�̂��B�l�Ԑ����A������������Ă������B
����قlj����Ă��̂͌��S�Ȑl�Ԃ̍��������Ƃ��Ă����B
�܂��A�N�����A�Á`���݂��߂ɂȂ�B�E�E�E�Ǝv���B
�m��ʂ܂ɋC����B
�����A�����ɖҗ�Ɏ�������K�����������Ă�ƁA���Ɓ`�`���ƋC���߂������B
����ȂƂ��A�T�ɂ��Ƃ������Ԃł������I
����������ł������猻��ɏo�ĘJ������I
���ꂪ�I���i�ɂƂ��āA���_�q���I�Ƀ��C�Ǝv���B
��삷��l�Ԃɂ��A���������߂����Ԃ��v��Ǝv���B
24���Ԃ��`�`���Ƃ����Ȃ��ŁA������Ƃ����O�ɂłē����B
���̂Ƃ��A����ς�A�l�����ĉ����H���ċC�����̂ǂ����Ńt�b�ƌ�邱�Ƃ�����B
�j���Q�����V������Ă��Ƃ̖{���𗝉��ł���C������B
����𗣂�āA���̏u�ԂɊ_�Ԍ�����^���Ƃł����������H
������āA���`�`���ƉƂ̒��ɂ���ƁA�Ȃ��Ȃ��A�^�}�ŗ����ł��Ȃ��i�ǂ��Ղ�Ђ��肷���ď��Ղ��邾���j�悤�ȋC������B
�v���҂ƁA���`���Ɛڂ��Ă���ƁA���Ȗʂ��������Ȃ����Ƃ�����B
�ł��A�s�v�c�����A�O�ɏo�ē����Ă��邳�Ȃ��ɁA�I�b�Ɨ����ł����肷��B
�l���ɂ��Ă��A�V����Ӗ��ɂ��Ă��B������ƃ��J�b�^�C�ɂȂ�B
���邢�v�l�����܂��悤�ȋC������B
�ǂ�ȃI���i�ɂ��J���N�w�͂���A�ǂ�قǍ��ׂł��낤�Ƃ��I���i�ɂ��l���N�w�͂���̂��B�����A�����\������̂��I�m�łȂ����A�\���ł�����^�����Ȃ�����������������Ȃ��B�I���i���������Ă��������̂����ŁB
�d���Ǝ����Ƃ������݂Ƃ́A�W���������ɗ����ł��ď��߂Đl�����t�s����Ӗ������B
���ꂪ�A�I���i���d�����āA�Ǝ����āA�q��Ă��āA��삷����Ă��������ł͂Ȃ����H
10�N�A20�N�̒�����i�V�l���͒��������������肩�����j���A�d����ʂ������Ԃƈꏏ�ɁA������s���A�S�z�������ׂ�Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��C����蒼���āA�悵���I�������撣�낤�I�����I�I�Ȃ��I�I�ƁA�v���B
�݂��ɗF��Ŏx�������Ȃ���E�E�E
������A�ǂ̐E���ɂ��d������߂Ăق����Ȃ����A�ׁX�Ƃł���������A�d���͑����Ăق����Ɗ���Ă���B
�d�����E�������̃J�E���Z�����O�ɂȂ�B���̑̌����炢���B
�܁[�[�[���������킯�ŁA����₱����13�l�I
�܁A���������킯�ł��B
���ꂪ�A�c�ɂ̃q�}�`�Ȉ�@�Ȃ̂ɁA13�l���E�������闝�R�ł���܂��B
�b��V�l���̊�@�I�ւƁA����Ƃ����߂��܂��B
�P�A���ꂩ��܂��܂��w���p�[���s������B
�Q�A�߂������A���ی��̍������V���[�g����B
�R�A�ƒ�ɃI���i�肪�K�v�B�ł��A���ꂾ���ɗ�����Ńz���g�ɒ������ł���̂��H
�S�A�l���̌㔼��ɂނ��āu�e�̉��Ǝ����̘V��v�v����������藧�Ă�ׂ��B
�T�A�V�l�����}���V�����̌��z�ƁA�����̔N���z�ƁA�������V���~���[�V��������B
�U�A���������Ȃ��삪�v��I���ď����ł��S�̒��ŗ\�����Ă݂�B�z�����Ă݂�B���̂Ƃ��A��̓I�ɂǂ�����ď���̂��H�܂��́A���ɏ����čl���Ă݂�I
�ȏ�A�@���́u�V���킱�Ƃ͂��߁v�ł����B
�j�n�n�r�̃u�[�c
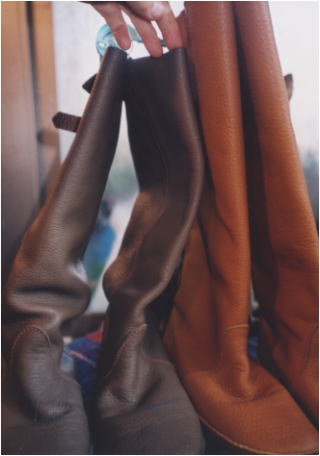
���̓~�́A�����܂��ɂ��A�j�n�n�r�̃u�[�c���͂��Ă���B
�j�n�n�r�̓����́A���̌C���ɂ���B

�C�ꂪ�A���̂̌����ɂ����ŁA�S��������i�r�[�`�T���_���j�𗚂��Ă��銴�G�Ƃ����Βʂ��邾�낤���B
�����ȌC��Œn�ʂ��Ȃł�A�Ƃ������u���葫�v�ŕ����Ă��銴���B
�C�ꂩ��A�n�ʂ̂ł��ڂ��Ƃ��A�����̊��o�܂ł����ɓ`����Ă���̂ŁA�܂�ŗ����ŃT�o���i�����邢�Ă��銴�G�i���������ƂȂ����j�ɋ߂��B
���������`�������ŁA�����������ƕ������o�Ȃ̂��B
�j�n�n�r�̃u�[�c�͂��ׂăq�[���̍������܂������Ȃ��A
�����̒�ɔ��`���S���������Ă��邾���ł���B
���������u�[�c�Ȃ̂ł���B
���������c�t�����̉J�C���ۂ��u�[�c���A�Ⴂ�q�Ȃ�܂������A50�߂����I�o�n�����N���������������ĂĂ��������̂��H�Ƃ����c�_�͂��Ă����B
�Ȃ��H�����j�n�n�r�̃u�[�c���D��ŗ����̂��H�ƌ����ƁA
���̗��R�́A����̃^�C�c���͂��āA���̏�Ƀj�b�g�̒��߂̃n�C�\�b�N�X���͂��āA���̂����Ńu�[�c���͂����߂ɂ́A�ӂ���͂��̕����ƍb�ɂ�قǂ̂�Ƃ肪�K�v�Ȃ��߂��B
���̏��������u�[�c�������A�j�n�n�r�I�Ƃ����킯���B
�j�n�n�r�́A�ӂ���͂����A�b���Ԃ��Ԃ��ł���B���ڂ��ڂȂ̂��B
���͍��܂ŁA�u�[�c���͂��Ƃ����ƁA���ɂ͔���̃i�C�����X�g�b�L���O�������B
���ꂪ�A�ǂ��������̂��A�ŋ߂̓^�C�c�ƃn�C�\�b�N�X���͂��āA���̏�Ƀu�[�c�𗚂��B
�ЂƂ��у^�C�c���͂��Ȃ��ƁA���ł����ɃX�g�b�L���O�������o��������o�����Ƃ��āA���̎���Ђ����߁A���ӎ��Ɍ���̃^�C�c����������o���Ă���B
�X�g�b�L���O�́A��߂���[�߂��B�ʂ����ق������������B�ƂȂ�B
���͂�^�C�c�Ȃ��ł́A����̕����O�g�ł͕s�o�ς��I�ƁA�v���B
�ȁA�ȁA�ȁA�Ȃ�Ōo�ς������ŏo�Ă���̂��H�C�L�i���H�s�o�ρH�H���ƁH�H
���̗��R�́A
�u�[�c�̉��Ƀ^�C�c���͂��āA��܂ƃ}�t���[�����āA�_�}�[���̃V���~�[�Y�𒅂邾���ŁA���ꂾ���ő̊����x��3�x���炢����Ċ������邩�炾�B
���Ă��O�g�̐���̒��������������Ȃ��B
���ꂪ�A�����X�g�b�L���O�ł́A�ǂ����낤�H�������܂ƃ}�t���[�ƃ_�}�[�����������Ƃ���ŁA��������₦������Ă���ɈႢ�Ȃ��B�̊����x�R�x�̈Ⴂ�͑傫���B
�f�Ò��ɂ��^�C�c���͂��Ă���ƁA���ꂾ���Œg��������g�[��p��ߖ�ł���B
����͎������B
�ł�����A����ɔ����X�g�b�L���O�őf�����ۂ��f�Â���ƂȂ�ƁA�������R�x�]���ɏ㏸���˂Ȃ炸�A�g�[��p�������ށB�d�C�オ���ˏオ��̂��B
�j�n�n�r�𗚂��悤�ɂȂ������R�̈�́A
�g�[��p��ߖ�ׂ����I���Ƃ��o�ϐ��ɂ߂��߂����Ƃɂ��B���͂����Ȑ����ȂB
���̓~�́A�Ζ��̒l�グ���Ō���������ȁB
�������A�{���͂��Ȃ��B����ς�A�₦�ǂ��ȁB
�X�N����Q�ɂ��ƍl������₦�ǂ��A�N�X�[���ɂȂ邩�炾�B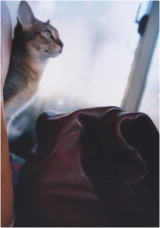
����A�Ⴄ�I�����Ɛ��m�Ɍ����ƁA
���N����X�N����Q���˔@�Ƃ��Č����������߂��B���N�A�ˑR�A�₦�ǂ������I
������A�^�C�c���͂��Ăj�n�n�r�̃u�[�c�𗚂��ďo����B
�u�[�c�̉��Ƀ^�C�c�ƃn�C�\�b�N�X���͂��悤�ɂȂ��Ă���i�I�o�n�����������I�j
�ӂƒʋΓd�Ԃ̎ԓ����ώ@����ƁE�E�E
�i�݂Ȃ���A�C�b�^�C�ǂ�ȑ����Ŏd���ɂł�̂������H�j
�Ƃ�킯�A�n�k�����̑��ɁA�Ȃɂ��Ɏ����������悤�ɂȂ����B
���̏��������̑������C�ɂȂ肾�����̂��B
�ʋΓd�Ԃɏ��ł���B
����ƁA������p�ԗ��Ȃł͂ł��ˁB
�w�A�X�^�C���A���C�N�A�o�b�O�A�R�[�g�̎��ɌC�ɖڂ��s���ł���B�ق��̏������ǂ�ȃJ�b�R�ŋ߂ɍs���̂��`���b�ƌ���Ƃ��������邶��Ȃ��ł����B������ƂˁB
�i�u�����h���v�Ƃ��A�A�N�Z�T���Ƃ��A�������������͂������ڂ��Ƃ��`�F�b�N�j
���̌��ʁA�킩�������Ƃ����A���딧�X�g�b�L���O�Ńp���v�X�Ƃ������ł����́A�~�̎ԓ��ł͊F�����Ƃ������ƁB
����͈ӊO�ł������B
�����̒ʋΓd�Ԃł���`�`�E�E����ȂɃI���i�������ς������āA�т����ƃX�[�c�Ō��߂đ����̓q�[���̍����p���v�X�I
�Ƃ������ł����̃L�����A�E�[�}���͈�l�������̂����ȁH
���Ȃ��B���Ȃ��̂ł��B��l�����Ȃ��B����͏Ռ��̎����ł������B
�݂�ȁA��������A�u�[�c���͂��A�ȁA�ȁA�Ȃ�ƁA�����̓^�C�c�ł͂Ȃ����I
���͂���܂ŁA�ʋ��L�����A�E�[�}�����q�[���p���v�X���{�f�C�R���X�[�c�I�Ə���Ɏv������ł����B�ʋn�k�͕K���n�C�q�[���𗚂��Ă���ƐM������ł����B
�ʋΓd�Ԃ̏��������́A�ӊO�ɂ��^�C�c�ƃu�[�c�h���嗬�ł��邱�ƂɋC������A�{���Ƀs���q�[���������Ă��Ȃ��̂��H�n�C�q�[���͂����̂��H�H
��l�����Ȃ����Ƃ��m�F���邽�߂ɁA�����������������ώ@����悤�ɂȂ����B
�����Ă킩�������Ƃ����A�������d�ԁi��ԍ��G���钩�̎��ԑсF�E�l���b�V���Ƃ��Ăԁj�ɂ́A�n�C�q�[���͂قƂ�ǂ��Ȃ��B�X�g�b�L���O���܂��������Ȃ��B���q�[���Ɍ���̌C�����Ă��������͂��邵�A�X���b�N�X����̂������`���C���ɒZ�u�[�c�ƃ��[�N�u�[�c�̒��Ԃ݂����ȑ���������B���������|�I�Ƀ^�C�c�������B�����ăS����B
���̎����Ɂu���������̃X�g�b�L���O�Ƀn�C�q�[���v�͈�x���������Ȃ������B
���̂��Ƃ��A�܂��M������Ȃ����́A�Ӓn�ł��n�C�q�[���������悤�ƁA�������͒ʋΗ�ԂŖڂ��Â炵�Ċ撣�����B
���������̑��������₭�A�������A���������`�F�b�N���������B
�������n�C�q�[���́A���̋G�߂ł��邽�߂��H��x�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
���͎����̐���ς�ے肹��������Ȃ������̂��B
���ǂ́A���̎v�����݂������E�E�E���������n�C�q�[���ɃX�[�c�ŏo����Ȃ�āE�E
���Ⴂ�������Ƃ��������B
�^�C�c�h�͓d�ԂƎ����ɂ���邪�i������p�ԗ��Ȃ���60���̓^�C�c�H�j���Ȃ��Ȃ��B
���������āA���������͔h���H�����ˊO�ł̃o�C�g�H�w���玩�]�ԁH�H�O�ł������H
����Ƃ��A�E��Ńu�[�c���p���v�X�Ɨ����ւ���́H���Ԃ��ɈႢ�Ȃ��B
���`�ށE�E
�����Ă��̃L�����A�E�[�}�����u�[�c�ŏo���Ă��鎖���ɁA���܂���C�������̂��B
�����āI�����Ƃ����ƈӊO�Ȕ����́A�u�[�c�̃q�[���������Ȃ��I
�ɒ[�ɂ��ł͂Ȃ����A�����č����q�[���ł͂Ȃ��B��߂̃q�[���ŏo����B
�������ɂȁE�E����������A������Ȃ��E�E�E
�w�̊K�i��҃X�s�[�h�ŏ�艺�肷�郉�b�V���A���[�ł́A�����q�[���ł悽�悽���Ă�����A�˂����Ƃ���āA�����ō��܂����˂Ȃ��B
�Ⴂ�q�[���ŗp�S���Ȃ��Ɖ���̂��Ƃ��ƁA�N���������낦�Ă���Ƃ������Ƃ��E�E�E
���݂����ɂi�q��芷���A���p���ɁA�K�i��҃X�s�[�h�ŏ㉺�������ɂƂ��āA��l�ł��̂�����O������l������ƁA�^�b�`�̍��ŏ��x��邱�Ƃ����邩��A���b�V���A���[�ł͂��ׂĂ̒ʋq�����������킹�ĕK���ŋ}�����Ƃ��A�Âɗv�������B
��b���厖�Ȃ̂��B
�n�C�q�[���ȂA�͂��Ă��Ă͂����ő���䂷��B
�������E�E�E
���ꂾ���A�Ⴂ�q�[���ƃ^�C�c���嗬�ɂȂ����Ƃ������Ƃ́E�E�E
���`�`�ޥ����̒��́u�������Ă����J�b�R���Ȃ��I�v�����ɐi��ł���B�̂�������Ȃ��ȁB�����̂ɔ����X�g�b�L���O�Ńn�C�q�[���p���v�X�Ȃ�āA�������ăJ�b�R���Ă邱�ƂɂȂ�̂����ȁH���v���̗v�Ȃ̂��B
�����ł킩�������Ƃł����B
�@ �n�k�����́i�n�k�Ȃ�Č��t�����łɎ��ꂾ�j�d���ɐ�O����B�^�����B
�A �n�k�i���͂n�k�Ƃ͌���Ȃ���ȁH�j�����́A�d���ɍs���̂ɂ���炿���J�b�R���Ȃ��B���������B
�B �n�k�����́A�J�o���ɕٓ��A�����A���ށA�V�������A�������ău�����h�łȂ�����̂������ł����Œʋ���B���ɂ͉p��b�̃|�b�h�B���Ӗ��ɋ���Q��Ȃ��B
�C �d���ɏo��ɂ́A���������ڂ��Ȃ��Ă��A�����Ă������Ȃ��B���������Ėh�����v�̃^�C�c�ƃu�[�c���͂��̂��B�O�ς������Ȃ̓��ʂɓ����Ƃ������Ƃ��H
���Ⴀ�A�Ă̎ԓ���������A��낯�����ȃn�C�q�[���ؚ̉��ȃT���_���͂͂��Ȃ��H
�����Ɖ��̂��邳���~���[�����͂��Ȃ��̂��낤���H�ǂ��Ȃ낤�H
�����Ȃ�����A�g�R�g���Ă̑������ώ@���Ȃ�������Ȃ����B
�I���i�������Ȃ����ȁB�Ǝv���B
�����܂����I���i�������Ȃ����Ȃ��B�Ǝv���B
��������������h���������āA��������ׂ����R�ɖh���A��������Ǝd���ɋ}���B
�悽�悽�����Ȃ��̂��B�ڗ����Ȃ�����������Ɨ͋��������B
���Ȃ݂ɌߑO10������ɂi�q�����w����d�Ԃɏ��ƁA
�ՎU�Ƃ����ԓ��ł́A���������ɏo�����鉜�l������A�ό���f�p�[�g�̍Â��ɍs���}�_����A���ǂ��̊w�Z�s���ɎQ�����邨��l�����́A���o�������Ƀq�[���B�Ƃ������ł�������������B
�����ł̓q�[�����嗬�����A�X�[�c���������邵�A�o�b�O�̓u�����h�����B
�����ȂE�E�E
�n�C�q�[���̓L�����A�t�@�b�V�����ł͂Ȃ����āA���o�������b�N�Ȃ̂��E�E
���������A�j���p�h�������I��������j�N���Ŕ����Ƃ��E�E�E�o�J���ꂵ�������ȁE�E
�������Ȗh�������V��j���Ƃ킸�A��������蒅���Ă����B����́A�������萶����A�Ƃ������L�`���Ǝd������j�����T�|�[�g����_�ŋ������̂�������Ȃ��B
���āA���͂ǂ��Ȃ낤�H�E�E�E
���́A���N�܂Łu������ƍ��߂̃q�[���u�[�c�ɃX�g�b�L���O�v�ŏo�����Ă܂����B
�R�[�g�̂Ȃ��ɂ́A�X�[�c�ł͂Ȃ��A�p���c�ƃZ�[�^�[�ƃ_�E���R�[�g�ł��B�z�̃g�[�ƃo�b�O�ɂ͕ٓ��Ɛ��������A�V���Ɩ{�Ə��ނ����Ė����d�Ԃɏ���Ă��܂��B
���������N�́A�j�n�n�r�i���u�[�c�j�Ń^�C�c�o�ł���B
���̗��R�́A
�@ �₦�Ǒ�
�A �g�[��ߖ���
�B 50���Ƃ����ɉ߂���Ɓi�ׂ����J�b�R���悤�j�Ƃ͎v��Ȃ��Ȃ�B
�C ����́A�J�b�R�Ȃǂ��̍ɂȂ�A�����ǂ��ł������E�E���Ă�������Ƃ̓`������
�Ⴄ�B�����̃I�o�n���X�^�C���Ɏ��M���ł����E�E�E���Ă����̂Ƃ������ɈႤ�B�������������ɃG�l���M�[�U���Ȃ��Ŏd�������ɏW�����邽�߂ɂ́A�d���ȊO�̃p�[�c�ɂ́A�ł��邾������Ĉ��S�A���N�A���S�̂R�������d������悤�ɂȂ����B
�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B�W������|�C���g���A�d���ɕΏd���Ă����Ƃ����b�B
�܂�A�d���ȊO�ɋC��z��̂�����ǂ��Ȃ����B�����l�͘V���Ƃ�ԁB
���{�@���́u���邭�y�����ߖ��̂����߁v
�킪�g�Ȃ��E�E�E���������^�C�g���ɂȂ��Ă��܂����I
���͐ߖ�Ƃł͌����ĂȂ��B
�Q����ɑ�����Ǝ����ł��v���B
�v��������A�݂������Ȃ��������g���܂����Ă���B�Ǝv���B���̂������Q��Ă�B
���Ƃ��A�{��B
�A�}�]���Ŗ���100�����炢�������A�V�������{���Ŗ���3���~���炢�����B
���̒��ŁA����͂Ǝv���������c���Ă����Ă��́A�����i������A�O���ɂ����A����j���邩��茳�ɂ͊�����c�炸�A���ƂɂȂ��Ă�����x�����{�����Ƃ��炠�邮�炢���B
����͘Q��ƌĂԂׂ���������Ȃ��B����A�Q��ɊԈႢ�Ȃ��B
�A�}�]���̖{��1�~�`300�~�ł������͍������A�V���͈��1000�`2000�~�͂���̂��B
�����K���{���i�i�q�\���j�ŗ����ǂ݂��邩��V���͂���ł��ڂɓ���A�[���ǂ݂������̂́A���킸�����Ă��܂��B������Q��ł��낤�B
�V���̓A�}�]���ł��قƂ�ǒl�������Ȃ��̂��B
�r�f�I��
����10�{���炢���B3500�~���炢������B
���͉ƂŃe���r���܂��������Ȃ�����A�Ƃ��ǂ��i�f�����������`�`���j�Ƃ�������ɏP����B�f�����]�ǂ��B
�����Ńe���r�����Ă��A���`�`���ƃe���r�̑O�ɍ����Ă��鎞�Ԃ��Ȃ��B
���̂�3�����e���r��ʂɐ����ł����ɁA���X�Ɖ�����Ǝ��ɒǂ��܂�����B
�Ђ傢�Ђ傢�����y���̂��B
�ł�����f�����c�u�c�ɂȂ��Ă��܂��B
����ɂ͘^��ł���s�u�i�X���W���i�̂s�u���j���Ȃ����烌���^�����邵���Ȃ��̂��B
�����i
���̃h�E���N�ł��B����������ɂ́A���傭���傭�������A���ΕK���������Ă��܂��B�����i�Ƃ����̂́A�o��̏u�Ԃ̒����Ŕ���Ȃ��ƁA���������x�Ɖ�Ȃ��V�����m�ł��邩��A�p�b�g���ăT�b�g�����I�̌J��Ԃ��Ȃ̂��B
���������ς�Q��ł���B�Փ������Ƃ�������B���500�~�`2000�~���炢�B
���傭���傭������邩��A���z����1���~���A���Ȃ����łT��~���A���̂��炢�͕K���g���Ă���Ǝv���B����̓��b�p���Q��ł��傤�ˁB
�m��
������o�[�Q����50���n�e�e�Ə�����Ă���ƁA�T�b�g�����Ă��܂����Ƃ�����B
�����l���Ă���ς蔃�����Ƃ�����B
�������������ɔ���Ȃ����Ƃ�����B
�����Ԃ�l���āA���Ĕ����ɍs���ƁA�����Ă��Ĕ����Ȃ��������Ƃ�����B
�ł��A�Ԃ��ƒʂ肪�����āA������Ɨ�������āA�������Ɣ������B�Ƃ����̂������B
���͎蒠�ɍ��N�̗m���v��i������́A�ǂ��������̂��A���������j�Ȃ�ė��Ă��Ȃ��ŁA���̏�̒����Ō��߂Ė��킸�����Ă��܂��B����͘Q��Ƃ����ׂ����낤�B
����Ȏ����ߖĂ���Ǝv�����ƁB
�H��
�O�l�̂��ǂ����������Ă���A�R���r�j�Ńf�U�[�g��y�p�b�N��Ȃ��Ȃ����B
�f�p�n����A�n���Ƒ����b�N�t�B�[���h�̑y�؉��ɂ��C�b�T�C�s���Ȃ��Ȃ����B
�y�p�b�N�́A���傿����Ɣ����Ă�5�l�Ƒ�����1500�~�`2000�~���炢�Ԃ���ԁB
���ǂ��Ɏ肪�������������́A���V�̂������ɒǂ���A���̕������ɁA�P�`�Q�i�ł��y�p�b�N������A�叕���肾��������A�����o�������y�̃`�J������Ă����B���ꂪ�Ȃ��Ȃ����B
���ł͂܂������y��Ȃ��B
���łɁA�ٓ��i���͒��A�Ӂj����}��Ԃ̒��ŐH�ׂ邩��A�d���̍��ԂɐH�ׂ钋�ٓ̕����܂߂āA���A���A�ӂ̎O�H���ٓ̕������Q����B�����ɂ͍g���B
�ٓ��͐ߖ��̑������Ǝv���B���ꂱ��20�N�߂��A�ٓ����Q�Ŋ撣���Ă���B
�H��͉��H�i�łȂ��āA�܂邲�Ƃ̑f�ށi��Ȃ��܂邲�ƁA���Ȃ��g�ł͂Ȃ��܂�̂܂܂̑N���j�������Ƃ������B��T�Ԃł��A�������@��ς���Ύg���܂킹�邩��B
�����ăX�[�p�[�ɍs�����������B���ꂪ�ߖ���ʂƂ��ẮA�����Ƃ��傫���B
���ϕi
��{�͕S�ρB���g�Ȃǂ�100�L���Ŕ��N�͂��B
�V�����v�[�ƃ����X�͔���Ȃ��B
���܂ŌŌ`�Ό��Ŕ��̖т����āA�Ȃ����Ȃ������̂ŃV�����v�[�������X�����������Ƃ��Ȃ��B���̔��̖т́A���e�@�łق߂���قǂ�₳�炳��ł��邪�A�{��������Ȃ��B�{�����������Ă���B�͂��꒼���I��������肾�B
�Ό��́A�I���[�u�I�C��100����450�~�̌Ō`�Ό����g���Ă���B
�Ō`�Ό��ł��A�Ƃ�킯�傫���ł��̂łS�`�T�����͏\�����B
���ɂʂ�N���[���́A�a�n�c�x�r�g�n�o�ƁA�H�p�̃G�N�X�g���o�[�W���I���[�u�I�C���B
�H���i�̐H�p���R�[�i�[�ɔ����Ă����ˁB500�~���炢�́B������380�~���炢�B
����́A���ϕi�Ƃ��Ďg�p���ĂȂ����Ȃ������̂ō��܂Ŏg���Ă����B
���v����Ɖ��ϕi�W�Ƃ��āA�N�Ԃ�2000�~���x���Ȃ��E�E�E
�|���p���
�ƒ�p�i�����ɂ́A�i�j�i�j��܁E�E�Ə̂��āA�p�r�ʂɂ�������̎�ނ̐�܂������Ă��邯�ǁA�K�v�Ȃ��Ǝv���B
�����x���̐����\�������Ă݂Ȃ�B�������������Ȃ�ĉ����Ȃ���B�܂������Ȃ��B
�Ȃ��݂̓J�X����B
���́A��܂͎g��Ȃ��ő|������B
�^�I���Ő@�������ŁA�������ꂢ�ɂȂ�B��܂��g��Ȃ��Ɖ���͗����Ȃ��I���Ă����̂́A�Ԉ���Ă���B�^�I����{�ł��ꂢ�ɂł����B����Ă݂Ȃ�B
�d���i�x�[�L���O�p�E�_�[100�~���炢�́j�����ł������A�Ō`�Ό��ŏ\�����ꂢ�ɂȂ�B
�Ό��Əd�������Ńs�J�s�J�ɂ��邱�Ƃ͂ł���B
���ƃJ�r�L���[��100�L���Ŕ������Ƃ����邪�A��{�͏d���ƃ^�I���ƌŌ`�Ό��B
�t���[�����O�̓A���R�[���i80�~���炢�Ŗ�ǂɔ����Ă���j���X�v���[���Đ@�������B
��܂̍��v���N�Ԃ�1000�~���炢���ȁB
�N���[�j���O��
���͂��ǂ������̃Z�[���[���������g���̃R�[�g���X�[�c���Ȃ̃g�����`���A���ׂĎ����Ő���B�ł��܂���B����Ă݂Ȃ�B�N�ł��ł��邩��B���ɂ��ł������B
�f�ނɃ��[�����Ȃǂ̉��@���܂܂�Ă��Ȃ��i���ł��тł��n�j�j�Ȃ�A����ł����Ɛ���ł��܂��B���[�����͓���Ȃ��B���A�Ă�Ă�ɂȂ��Ă��܂�����B
�ł��������̑O�ɁA�����h���[�̃^�O�͂�������m�F�B
�Z�[���[���̂悤�Ƀv���[�c�������Ƙr�͏����B�������̏�ԂŃA�C������������B
�E�����Ă��d�������Ԃ������邵�A���������d�J���ł����A���̕���肪���������ł���B
���ꂢ�ɐ��������Ƃ��ɂ́A���b�^�[�Ƌ��т����Ȃ�B
���P�������Ő���ł����B
�N���[�j���O��̓[���B
�N���}
�R���̏W���ł���O�g�s�ł́A�ǂ��ɍs���ɂ��N���}�͕K���i�Ȃ̂ŁA���ÎԂ͕K�{�B
�����i�q�����p���ŁA����ɎԂ��^�]���āA�����ʋ���B
�N���}���Ȃ���Α傫���ߖ�ł��邪�A�N���}���Ȃ���Ύd���ɍs���Ȃ�����A�ǂ����Ă��N���}�Ȃ��Ő������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��������肾�B
�s��ł̓N���}�Ȃ��I�Ő������邱�Ƃ��ߖ�̑������Ǝv�����ǁB
�m�����̑�
�����A�߂����ς��Փ����������̂��m�����Ƃ��āB
�����Ƃ��C���p�N�g�̋����A�C�e���Ƀh�J���I�I������������ށB���낵�����z���B
�R�[�g�Ƃ��W���P�b�g�Ƃ��B���z�ł��S�O�����ɔ����Ă��܂��B10�N�͒��邩��B
�ڗ��Ƃ���ɁA�h�o���Ƒ���𒍂����݁B
����ȊO�̓��j�N�����A���t�[�̃I�[�N�V������500�~�`1000�~�B
�~�́A�u�[�c�𗚂�����V���[�g�p���c�ƃZ�[�^�[�A���ɂ̓V���c�B���̃p�^�[�����������A���Ȃ݂��V���[�g�p���c�̓��j�N����500�~�B300�~�̃E�[���p���c������B
�I�[�N�V������nitca�@�H�i�Ȃ�ēǂނ��킩���j���[�J�[�̒Z�p���c��3���w���B
�V���c�̓o�[�Q���B�Z�[�^�[�����z�B
����ɂ��Ă��A��������Nitca�͂ǂ��������[�J�[�Ȃ낤���E�E�E�_�{�_�{�Z�p���B
�j�n�n�r�@�̃u�[�c�����Â��I�[�N�V�����ōw���B
�C�̓u�����h�𗚂��Ȃ��B��ł����Ⴎ����ɂȂ邩��B�������j�n�n�r
�͂悩�����B
�J�o�����u�����h�͔���Ȃ��B�ٓ��̏`�łׂ���ׂ���ɉ����̂��ڂɌ����Ă��邩��B
������10�N�ȏ㒅�����ɂ́A����𓊓����āA���Ƃ��Ƃ��܂Œ���B���������āA
15�N���炢���邱�Ƃ��ł������Ɏv���B���߂��Ȃ��E�E�E
�i50����65�܂œ����J�b�R�ł��������������E�E�H�H���Ƃ܂������E�E�E�j
�����Ă��ςރA�C�e���́A�Ƃ��Ƃ�������̂��B
���̎g���������|�C���g���ƍl����B
�G�N�T�T�C�Y�̃E�G�A
����͂ł��˂��B���́A�����}�_�����猩����A�݂��Ƃ��Ȃ��E�E�_�T�C�E�E�E�����E���̂̊i�D�ŃW���ɍs���܂��B
�W���p�̃E�G�A�͐��N�O�i���Ԃ�S�N�O�H���������H�H�j�ɁA�V�����̂��h�b�T�������܂��āA���̑O�ɔ������̂��m��15�N�ȏ�O�ł�������A���`�`����ŁA�����Ԃ�V�����Ȃ����I�Ə���Ɏv������ł��܂������A�����}�_���͖����H�V�����E�G�A�H�H�ʼn^���Ȃ����Ă��܂�����H4�N���O�̂��̂𒅂Ă������E���̂ł��B
�����̃W���͍ŐV�̂��ł����̕��������ł��B
�C���^������̐V�^�A�܂��܂����������Ȃ̂ɂȂ��E�E�E
���̐����͂P�T�N�ȏ�O�̂��̂ł��āA�����C�J���Ǝv���܂����B
���̃J�b�R�́A�N���ǂ����Ă�����x��ł��B
�����ŁA�����A�����Ȃ�����A�t�c�E�̉^�����i�s�`�s�`�̃��I�^�[�h���ł͂Ȃ��āA�f�p�����ǂ��Ƀg���[�i�[�j�ŃG�A���r�N�X�����Ă��܂��B�ق��Ƃ��Ă���I�I
���̏���ł��I���ƁB
���ꂪ�A�܂��A����ł��ł����ł��B�ł��܂��I
����Ă݂�ƁA�ӊO�ɂ��A�t�[�h�t�g���[�i�[�ƁA���ڂ��ڂf�p���Ń`�����Ɠ����܂��B
���I�^�[�h�łȂ��ᓮ���Ȃ��I�L�k���݂łȂ��ƃA�J���I�̂т̂щ��@�łȂ���_���I
�Ƃ����͎̂v�����݂������̂ł��B����Ă݂Ȃ�B�ł��邩��B�\���������B
�Ƃ����킯�ŁA�������t�c�E�̂s�V���c�ƃg���[�i�[�ʼn^�����Ă���܂��āA�Ȃ��s�s���͂���܂���B����ɁA���K���A���������t�c�E�̃J�b�R�ł�낤�Ǝv���ł����ł���B�ł��܂��B�ł��܂����B�ł���̂��B
�ł�����A�t�c�E�̊X���ł�����ł���B�W���ł̉^���Ȃ�āB
���̓g���[�j���O�p�ɍŐV���̃E�G�A�����낦��͖̂��ʂ��Ǝv���܂��B�ߖ�ׂ��B
����
����́A�_�}�[���̉�����20�N���Ă��܂��B
20�N�����܂���B���v�ł��B�j��Ă��Ă��U���Β����܂��B
���ہA�������������j��Ă��܂��������V�C�B�܂��܂������܂��B���傿����ƑU���B
���Ȃ݂ɁA�X�g�b�L���O�̓Z�V�[���̃X�[�p�[�n�[�h�T�|�[�g�B
�����1��2680�~�łT�N�͂����܂��B
�������Ă͂f�p���Œʋ��邩��\�b�N�X�ƃX�j�[�J�[���������Ȃ����A�~�̓^�C�c�Ȃ̂ŁA�����ɏH�Ət�ɃX�g�b�L���O���͂��킯�ŁA4�`5�����̒��p���Ԃł����A���ꂪ2680�~��5�N�͂������������B�D����̂ł��B
�ȏ�ł��˂��B���ȓ_�͑��X����܂��B�Ȃɂ���Q��Ȃ��h�h��ł�����B
�������ߖ�̃|�C���g�́A�����Ă��܂����B
�Ȃ�Ƃ����Ă������i�ٓ����Q�j���|�C���g�ł��B�H�ނɔ����H�i�킸�ɁA�܂邲�Ƒf�ނ��甃���ė�������ƁA���Ȃ�ߖ�ł��܂��B�ٓ����Q���厖�ł��B
���͗����������ɂȂ�Ȃ�����A����Őߖ�x���͂��Ȃ�㏸�I
���ƁA�①�ɂ��|������B�①�ɂ����傿����Ɣ`���܂��B
����͐^���ɉ��̂ق��܂Ŕ`���Ȃ��ƁA�Ƃ��ǂ����q���������܂��B
���ɉB��Ă���܂��B
���q���E�E�E
���̓_�A������Ƃ̎�Ԃł������疈���A�①�ɂ��T�b�g�@���|������ƁA���̂ق��ɂ������c�蕨���ł�����B
���[�[�܂��g���Ă��Ȃ��H�ނ������Ă������`�`�����g��˂I�Ƃ�����ɁA���ʂȔ������𖢑R�ɖh����B�������ɁA�Y���ꂽ�H�ނ������Ă����̂��ł��܂��B
���͑�^�①�ɂ��g��Ȃ��̂ŁA�����̂ق��A���݂����̂ق��A�ƌ����Ă����������m��Ă���B���a30�Z���`���x�̎���w�c�ł��傤���B
�Ȃ��^�̃`�r�①�ɂ�����ˁB�ɂ�������炸���q�͕K����������̂�����s�v�c���B
�����ƕs�v�c�Ȃ̂́A�①�ɂ��������̂���������邱�ƁB
���ɁA�{�ƃr�f�I�ƍ����͎��̃h�E���N�Ȃ̂ŁA�{�͂Ȃ�Ƃ����đ�����Ƃ��āA�������ɑ����^�ԉ����炷�I���ꂪ�|�C���g�ł��B
��������Ȃ��B�s���Ȃ��Ⴂ����ȁB�ߊ��Ȃ��悤�ɂ���ׂ��B
�Ȃ�ׂ�����������ɂ͍s���Ȃ��悤�ɂ��悤�I
�ӂ��ƌ��Ă��܂��ƁA�����Փ��������Ă��܂��I�I�s�������炷�I
���ɁA�m����Ȃ��I����͂��Ȃ茵�����I���������Ă��܂����낤�Ȃ��E�E
���Ԃ��Ă��܂��B������ĕa�C���낤�Ȃ��E�E�E�o�[�Q�������E�E�E
�����ŁI�����|������Ƃ��ɁA������Ɖ�����̒����|�����āA�ǂ�ȗm�������������Ă���̂��H�����Ŕc������B�蒠�ɏ����B�����āA��ɂ��̎��ʂ߂�I
�i�����̓N���[�[�b�g�ɖ{�����[���Ă��邽�߁A�m���͉�����̃u�b�N�P�[�X�ɂ�����ł��܂��Ă���B�{�����o�����m�������o�������������߁A�����Ȃ����j
������J��Ԃ��ƁA�ǂ�������ނ̗m�������������Ă��邩�H��ɏ�ɔ]�ɃC���v�b�g����܂�����A����ɁA�����悤�ȗm���͔���Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B
����ƁA�蒠�߂u�����Ă���Ȃɂ����m��������܁`�莝���Ă���v���Ė������ɂЂ���邩��A���ꂾ���łЂ����Ƀj���}���ق����݂Ȃ���A�S���I�Ɏ��Ȗ����ł��Ă��܂��B�V���ɔ���Ȃ��Ă������ł���S����Ԃ�ۂׂ��B
�܂��E�E�����ƒNj������
���������m���̐�ΐ������炷�i���炭���Ă��Ȃ����������j�ƁA����ɐ������ȒP�ɂȂ邩��A�������炷���ʂ͉��������Ǝv���̂ŁA
�����I�Ȑߖ�@�Ƃ��ẮA
�m���̐�ΐ������炵�A�����炵�����A�����đ��₳�Ȃ��B
�Ƃ������Ƃ��낤�B
�����̗m���̓��e�Ɛ���������Ɣc������ׂ��I���ꂪ�ߖ�̃|�C���g�ł��傤�B
����ɁI
�Ȃ��H�ߖ�̂��H�ߖK�v�Ȃ̂��H�ߖȂ���i�����̂��H�H
���̂�������S�ɐ������āA�蒠�̎��ʂɋL�ڂ��A���X���ӂ�V���ɂ����B
���ꂪ�d�v�ł���܂��B�[�w�S�����ɂ߂邱�Ƃ��|�C���g�ł��傤���H
�Ƃ������Ƃ́A�ߖ�̓_�C�G�b�g�ȂƋ��ʂ���u�[�w�S�����v�Ƃ��l������B
���Ԃɂ���ߖ�{
�x�X�g�Z���[�Ƃ������A�d�C��A������A�K�X��A�g�є�p�̐ߖ�W�̖{�ł����E�E
���������������������u�`�}�`�}�Ƃ�����ς���ΎR�ƂȂ�v�ӂ��̐ߖ�o�C�u�����āA�ǂނɂ͓ǂނ��ǁA���̂Ƃ�����s�ł��Ȃ��i���^�N�V�͓��Ɂj�l���Ă����Ȃ��́H
���^�N�V�͐�ɂł��܂���B�߂�ǂ������B���������Ȃ��B�̂ŁA�����l���܂��B
�u������ς���ΎR�v���ۂ��ߖD���ōD���ő�D���Ńn�}�b�e���l�͕ʂƂ��āA
����͖����B����͊֒m���Ȃ��B����Ȃ���I�ǂ��ł��C�C�I�Ɗ����B
���^�N�V�͂������܂��B�������܂��B�����Ă���ǂ������B
�ł������R�ł������R�������d�_�I�ɐߖ�B
���^�N�V�̏ꍇ�́A�ł������R���Ȃ킿�u�m���ƍ����̏Փ���������߂�v
�ł������R��ߖ邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃɂ����W���������B
���^�N�V�̏ꍇ�́A�ЂƂ��ƂōςށB
�܂��V���b�v�ɍs�������炷�B
�����āA���������L����m���ƍ����̐��X���蒠�ɏ����o���A�ʐ^�ɂƂ��Ď��ʂɓ\��t���A���X���߂�B���ꂾ���łn�j�B
���ɁE�E�E
�Ǝ������܂߂ɂ��B���ꂪ�ߖ�̏����B
�Ǝ��Ƃ����Ă��A�����h�̉Ǝ��ł͂Ȃ��B
���Ƃ�����炵�̎蒟�Ȃɂ����u�̂Ȃ���̉Ǝ��v���Ă����`���I�Ǝ��̒B�l�����̖����Ȃ�ǂނƃw�R���̂ŁA��ɓǂ݂܂���B�ł����܂���B�C�`�I�E�B
��炵�̎蒟�̎ʐ^�́A���[�[�[���ƒ��߂܂��������͓ǂ܂Ȃ��B��ɓǂ܂Ȃ��B
�C���߂���B
����ɂȂ�B
���������B
�킽���ᖳ�����`�`���ƃw�R���B
�������u�B�l�̉Ǝ��v�u�S�l�̉ƒ뗿���v�Ȃ������Ƃ��Ĕ���錻�����l���Ă݂�I
���܂ǂ��N���A�����h�̉Ǝ������Ȃ�����A���������u���������̐̃i�c�J�V�܂ڂ낵�̉Ǝ��V���[�Y�v�݂����Ȗ{��������ł���H�Ⴄ�����H�H
�����I���i�����傿����ƉƎ���������A���������u�����h�v�ł͔��Ē��������Ȃ��B�ŏ�����A�`�b�g�����C�ɂȂ�Ȃ��B�ł���킯�Ȃ������B
���^�N�V�́A�����������������Ǝ��͂ł��܂���B�C���Z���̂��B�Ƃ��������Ԃ��Ȃ��B
�ł��Ȃ����̂͂ł��Ȃ��̂��B
���쐳�q����i�����D���ȊG�{��Ɓj�������u���傪����Ȃ玩���ł����b�I�v
���̉Ǝ�����i���v�Ёj1400�~���C�C�Ǝv���܂��B
�����������������i�G�{��ƂƂ��Ĕ��Q�̗͗ʁj���A�����ł��Ȃ��̂ɁA���̂܂ɂ��Ǝ�������Ă��āi���삳��̔N���73�j
�ӂ��ƐU��Ԃ����u�����ɂƂ��ĉƎ����ĉ��������̂��H������ōl���悤���Ȃ��������Ǝ��̗��j���E�E�悭���܂����炭�Ǝ��Ƃ���������Ȃ��v�݂����Ȗ{���D���ł���B
���삳��̖{�����x���ǂݕԂ��āA�ӂ�ӂ�Ƃ��Ȃ����Ă���B
���삳��̉Ǝ��͕K�v�Œ���Ȃ̂Ƀ������Ȃ��A�B�l����Ȃ��̂ɐ^�������Ă���B
�Ǝ��̒B�l�ł͂Ȃ��i������w�̕Ў�ԁj
������A�^���i�Ǝ��ɐ^��������Ƃ���Ȃ�j�ɓ��B�ł���̂��H
���邢�́A70�Ȃ̂�30��ƕς��ʊ���������^�����ǂ߂�̂��H
���^�N�V�͏��삳����Ǝ��N�w�ɐ[����������ƂƂ��ɁA�������ߖ�Ƃ����T�O��t������ƁA�����Ƃ��������㕗�ɃA�����W�ł���ƍl����B
�܂��Ǝ����ߖ�Ƃ����T�O�́A���̍�����l���N�w���͂��ł���Ǝv���̂ł���܂��B
���_�ł��B
�ߖ�ɂ́A������ς���ΎR�ƂȂ�E�E�ł͂Ȃ��B
�ŏ�����A�f�b�J�C�R�����ɏd�_�I�ߖ�����u����ׂ��B����́A���̍ۂǂ��ł��C�C�B
�ߖ�̊�{�́A�����ł܂߂ɉƎ������B�ɂ���B
���̍���ɂ͐l���N�w���K�{�B
�N�w�������܂����ƁA�u�Ȃ��H�Ȃ�̂��߂ɁH�ǂ����āH�v�ߖ�̂����o�̂Ȃ��܂܂ɏI��邩��A�B���������������Ⴂ�B�Ǝv���B
�������Ă��Ƃ��������ȁH
�Ȃ��H�Ȃ�̂��߂ɁH�ǂ����āH�����͓����̂��H�ȒP�ł�������u�N�w�v������Ǝv���B
���́A���l����Q��i����Ȃ�����Ȃ�̘b�j�͔ے肵�Ȃ��B
���A���l�̂Ȃ��ߖ�����肦��Ǝv���B
�ߖ�̂��ׂĂɁA�������ɉ��l������Ƃ͍l���ɂ����B
�ߖ�Ȃ��Ȃ��ق����n�b�s�[�Ȃ�A���Ȃ��ق����C�C�B
���āA���̐ߖ�N�w�ł����E�E�E
�j���Q�����āA�Ō�̍Ō�܂Ő����邽�߂ɂ������v���ł���ˁB
�����A�ߖ�ɈӋ`�Ɛl���N�w�����߂�悤�ɂȂ������R�ł����E�E
�v�̕��e�̍Ŋ����Ƒ��ł̂肱�����Ƃ��A�j���Q�����āA���ꂢ�Ɏ��˂Ȃ����̂ȂȂ��E�E�ƁA���݂��ݍl�������Ƃ��傫���B�v�̕��e�ɑ����āA�v�̏f���A�v�̋`���̔����Ȃ������ĖS���Ȃ�A�������̃j���Q���̎��ɐe���Ƃ��đΖʂ����B
�j���Q���̍Ŋ��́A���L���C���������A�f�����̏L�C�͎��͂̂��̂��ׂĂ��Ȃ��|���A�������݁A�Ƒ������敾�����A�g�̂Ɛ��_���Ƃ��ɕa�܂��A�����ĂȂ��Ȃ��I�����}���Ȃ��B
���ꂵ���Ŋ��B�����E�E���������ȏX�Ԃł���B
���ꂪ�j���Q���ł���B�j���Q���̍Ŋ��Ȃ̂��B�j���Q���̂����O�B
�j���Q���̋Ƃƍ��̉��O�����������A�߂�߂�ƁA���͂��Ă��s�����B
���ꂪ�j���Q���̍Ŋ��ł���B
���������n���̓�������A�����Ƃ��g�߂ɑ̌��������́E�E
�j���Q���̖{�����������Ɗ������B�����āE�E�E
�l���̌㔼��ɓ�������A�Ŋ��܂ł̃v���O������S�ŏ������āA������̒����łǂ������l���̏I���𑗂�̂��H�����Ɓi�Ȃ��Ȃ������Ƃ͂ł��Ȃ����j�v�悵�Ȃ��ƁA�l�����āA�I����Ă�����P���Ȃ��ȁE�E�Ɗ������B�I����Ă���P���E�E�E
�l�����P���̂́A�Ȃɂ��s�N���̋Ɛт����ł͂Ȃ��B
�l���́A���̐l�̍Ŋ��̌}�����A�߂������ɂ���āA�c���ꂽ�l�X�̂�����̂Ȃ��ŁA���܂ł��������P���̂��B
�t�ɁA�Ŋ����X���ƁA�c��Ƒ��ɂ��ꂢ�Ȉ�ۂ��c���Ȃ��B
���܂ł��f�����̋C���ƏL�C���c��悤�ȋC������B
�Ⴂ�Ƃ��ɂ́A�܂������l���Ȃ��������Ƃ��B����v�������Ȃ������B
�����́A
�v�̕��e�Ɛe���̍Ŋ���������Ȃ���A��邱�Ƃ��ł��Ȃ������^�����낤�B
�Ŋ��̂����߂̂��������A�����̑��ǂŌ��܂�킯�ł͂Ȃ��B���������z�͊W�Ȃ��B
�Ƃ��v�����A���⒙�����Ȃ��Ɛl���̍Ŋ������܂�Ȃ���ȁB�Ƃ��v���B
�Ƃ�����
�㔼��ɓ�������A�Ŋ��܂ł̃v���O���������g�̐S�ɗp�ӂ��āA�Ȃ�ǂ��O���C�����Ȃ��玩���̃V�A���Z�̂�������T��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���B
���̋O���C���̃v���O�����̈�ɁA�����������āA���̔w�i�ɂ͐ߖ���B
�V�A���Z�̂������́A�N�X�ϖe����B
���̕ϖe�ɂ��킹�Ď����v�悪�����āA������x�����i�̈�ɃV�A���Z�Ȑߖ���B
�܂��E�E���������킯�ŁE�E�E
���ꂩ��́A�ߖ�I�Â��ߖ�ł͂Ȃ��u���邭�y�����������v
�V�A���Z�Ȑߖ��ɗ�����I�ƍl���Ă���B�l���㔼��̒������������Ȃ���B
�����āA�������Ă̂́A���ǂ����S���Ɨ����āA�͂��߂Čv��ł���Ȃ��E�E�ƌ���Ă���B
|